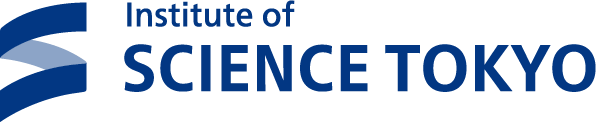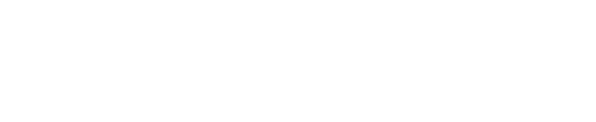データベースや電子ジャーナルを利用する際は、著作権法や提供元の利用規約・利用条件等を厳守し、適正な利用を行う必要があります。
データベース・電子ジャーナル提供元の多くが利用規約・利用条件等を定めています。
どの提供元においても、以下のことは禁止されています。
- 個人利用の範囲を超えた大量のデータをダウンロードすること
- 個人の学術研究および教育以外の目的で使用すること
- 複製や第三者に再配布すること
- その他著作権法に違反すること
利用規約等に違反する利用がなされた場合、一個人の違反行為であったとしても、大学全体に対して利用停止等のペナルティが科せられ、本学の学術研究・教育活動に重大な損失を与える可能性があります。
また、データベース・電子ジャーナルは大学として提供元との間で有料の利用契約を結んでいます。利用できない場合の経済的損失についてもご勘案くださるようお願いいたします。
たとえ技術的には可能であっても、規約上、行って構わないこととは限りません。
著作権法について
図書・雑誌等の紙媒体に限らず、全ての著作物には著作権があります(但し、憲法その他の法令等、例外を除く)。インターネット上で提供される文字・写真・図形等の情報についても、入手は簡単ではありますが、著作権法で著作権者の権利が保護されています。
著作権者に無断で他の電子メディアや印刷物等に転載したり、改変したりすることは、非営利の研究目的であっても行うことはできません。「入手したものは自分の自由にして良い」ということではありません。
利用規約・利用条件等
詳細は提供元毎に異なりますが、全てに共通する禁止事項は以下のとおりです。
1. 個人利用の範囲を超えた大量のデータをダウンロードすること
機械的にダウンロードすることは契約違反です。例えばキーワードに合致する文献を、ソフトウェア等を使用して一括または連続して表示したり、ダウンロードしたりすることは認められていません。手動であっても、一定時間ダウンロードだけを繰り返したり、ジャーナルの1号全ての論文を一括してダウンロードしたりといった、網羅的・系統的なダウンロードは適正な利用とはみなされないことがあります。
提供元は、アクセスログにより、不正な利用が行われていないかを常に監視しています。提供元が適正ではないと判断した場合には、アクセスを遮断する等の措置がとられます。 ”大量” ”適正”の範囲については、具体的な件数が一様に決まっているわけではなく、提供元の規約・判断次第となりますので、学習・研究を進める中で必要となった都度、必要な論文だけを利用するようにしてください。
また、意図せず不正利用してしまうことを避けるため、以下の点に注意してください。
- 文献管理ソフトウェアやそのアドオンの中には、閲覧中のウェブサイトから自動的に論文等のフルテキスト取得情報を収集する機能を持つものがあります。それらの機能は解除してご利用ください。
- 最近のwebブラウザには「リンク先読み機能」が組み込まれているものがあります。この機能が有効な状態で電子ジャーナルやデータベースを利用すると、バックグラウンドでリンク先のページ読み込みが繰り返され、意図せず過剰アクセス/大量ダウンロードをしてしまうことがあります。以下の手順で、お使いのブラウザの「リンク先読み機能」を無効化して電子リソースをご利用ください。
-
Microsoft Edge:「設定」>「プライバシー、検索、サービス」>「Cookie」を開き「ページをプリロードして閲覧と検索を高速化する」をオフ
-
Google Chrome(Windows):「設定」>「パフォーマンス」>「ページをプリロードする」をオフにする
-
Safari (Mac):メニューバーの「Safari」>「環境設定」(または「設定」)を開く。「検索」タブの「バックグラウンドでトップヒットを事前に読み込む」のチェックをはずす
-
Safari(iOS、iPadOS):「設定」>「Safari」>検索「トップヒットを事前に読み込む」をオフ
-
- 取得したデータを、テキスト/データマイニングや生成AI等に利用したり、クラウドサービスへアップロードしたりすることは禁止されている場合があります。事前に提供元の利用規約や禁止事項をよくご確認ください。
教育・研究のために、どうしても大量ダウンロードや規約外の利用が必要となる場合には、提供元に許諾が得られるかを相談しますので、事前に図書館にお問い合わせください。
2. 個人の学術研究および教育以外の目的で使用すること
個人の学術研究・教育目的以外の目的で利用することは契約違反です。
3. 複製や第三者に再配布すること
データベースや電子ジャーナルは、本学が契約を結んでおり、利用者の範囲は本学に所属する教員・学生等に限られています。検索結果を第三者に提供することは契約違反です。
アクセスが停止された例
- 特定の電子ジャーナルの2年分のデータをある研究室がダウンロードしたため、翌日にアクセスできなくなりました。提供元から警告メールが送られ、対応が遅れた場合には全学の利用が停止されかねない状況でした。 該当者を特定して研究室の先生に連絡し、本人には厳重注意と共に始末書を書いていただき、図書館から提供元に報告しました。アクセスができなくなってから、5日後に復旧しました。
- ある研究室で、特定の電子ジャーナルの2巻分のデータをダウンロードしたため、所属ネットワークからのアクセスができなくなりました。警告メッセージは出ていたはずですが、図書館への問い合わせがないまま数日が経過した後、「20日以内に事象の報告をしないと全学のアクセスを停止する」との警告メールが図書館に届きました。期限内に報告しましたが、提供元の事情で復旧までに4週間以上かかりました。
- ある研究室で、情報基盤センターが運営するプロキシサーバ経由で電子ジャーナルにアクセスし、本文のHTMLの表示を連続して行って表題のみを確認していたところ、1時間以上続けているうちに、アクセスができなくなりました。閲覧するだけでもダウンロードとしてカウントされていたためです。警告メールを図書館で確認したときには、既に同じプロキシサーバに接続している他の研究室からのアクセスも全てできなくなっていました。提供元への事情説明に努めましたが、アクセス再開には2週間かかりました。
- ある研究室で、ブラウザのタブ保存機能を有効にしていたところ、保存されていた電子ジャーナルのPDFファイルが起動時に自動的に開いたことが原因で、アクセスが遮断されたという事例がありました。意図的に大量のダウンロードをしたわけではなくとも、短時間に複数回再起動したり、多数のタブを開いた状態で保存していると、過度のアクセスと見なされることがありますのでご注意ください。
- ある学生が電子ジャーナルにアクセスし、約1時間の間に論文検索、約10件の論文ダウンロードをしたところ、アクセスができなくなりました。提供元からは1分間に100以上のアクションがあったため、アクセスを遮断したとの連絡がありました。大量のダウンロードをしたわけではなくとも、短時間に一定以上のアクションがあると、機械的な作業を疑われ、アクセスが停止されることがありますのでご注意ください。
※1.~4.の場合、ダウンロードしたデータは破棄していただきました。